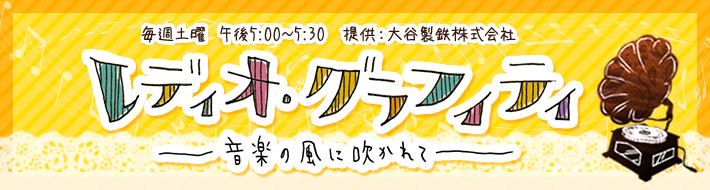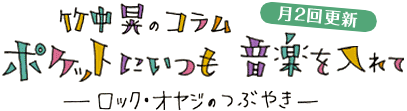第94回 “ザ・タイガース”~あの頃の記憶

来月、ザ・タイガースがオリジナル・メンバーで復活するという。
ジュリー、サリー、トッポ、タロー、ピー、こうして名前を聞いただけでも懐かしさがジンワリこみ上げてくる。
考えてみると、ジンワリ来るのはリアルタイムでタイガースを知っている50代半ば以上の世代になる。ということはこの年代よりも若い皆さんは知識としてタイガースという名前を知っているか、あるいはまったく『なにそれ?野球?』状態の人たちとなるわけで、おそらく後者が圧倒的多数を占めるに違いない。時間が経つとはそういうことだ。
もっともあらゆるモノゴトにマニアは存在するのが世の常なので、二十代のグループサウンズ・マニアという人もいるかもしれないが、それはさておき。
日本の音楽シーン(といっても歌謡曲がすべての時代だったが)に突如として巻き起こったグループサウンズ・ブームは、1966年3月にジャッキー吉川とブルーコメッツが「青い瞳」を、そして同年9月に田辺昭知とスパイダースが「夕陽が泣いている」を共にヒットさせたことが基点だった。ちなみに、この年の6月末にビートルズが日本公演を行っている。つまりは“そんな年”だった。
ビートルズを始めとする欧米のロック・グループの活躍に影響を受ける形で始まったグループサウンズだが、実のところはブームが過熱するにつれて欧米のロックのサウンドとはまったく違ったサウンドに、つまりは“エレキバンド・スタイルの歌謡曲”になっていった。したがってこのムーブメントを“グループサウンズ”という“日本的英語”で表現したのは皮肉にも的を射ていたことになる。
ただ、それにしてもブームのピーク時には玉石混交の状態ながらも三百組近いプロのバンドがひしめいていたわけで、それは確かに日本のポップシーンにおいては未曾有の出来事だった。
また、ベンチャーズの日本上陸以降、いわゆる日本における第一次バンド・ブームが起きたわけだが、グループサウンズ人気によってその動きがさらに加速することにもなった。
そしてそんなグループサウンズを過大評価し、結果として“社会現象”にまで押し上げたのは教育機関だった。彼らは中高校生に対して“不良になる”という理由で、グループサウンズの真似をしてバンドを始めることやグループサウンズのコンサートを観にいくことを禁ずるお達しを出した。そしてこのような状況が波及的に全国に拡がり、次第に大きな話題に、つまりはグループサウンズがブームを超えて“社会現象”にまでなったのだ。
さて。とにもかくにもそんな狂騒状態のど真ん中にいたのがタイガースだった。ジュリーというスーパーアイドルを擁するタイガースこそがグループサウンズ・ブームの頂点だったのだ。
そんな絶対的王者のタイガースにもライバルはいた。ライバルがいることでストーリーがより過熱して活性化するのは、源氏VS平家や、豊臣VS徳川といった古の時代からの常識だが、タイガースのライバルとして存在したのはテンプターズだった。
人気投票などの結果ではダブルスコアでタイガースの圧勝なのだが、とにかく芸能メディアは二大アイドルとしてタイガースVSテンプターズの対立図式を煽った。
例えば、当時の芸能メディアを代表していた月刊誌の「明星」や「平凡」では記事はもちろんのこと、どちらかがタイガースの特大ポスターが付録だったとしたら、もう一方の雑誌の付録はテンプターズのポスターだという具合に。
こうした芸能メディアの煽りを受けた結果、当時の単純な中学生はまんまとタイガース派かテンプターズ派かという抗争の構図に巻き込まれて、中学のクラス単位でもそのバトルは繰り広げられるに至ったのだ。
そしてこの抗争はバンド同士の団体戦だけではなく、タイガースのジュリーVSテンプターズのショーケンという個人戦でも行われたのだった。
そういえば『竹中クンはタイガース好きだよね!』と、隣の席の少し可愛い子に凄まれたことは憶えている。
タイガースは当時NTV系列で放送されていた<シャボン玉ホリデー>にレギュラー出演していて、毎回必ず一曲は演奏していた。そんな演奏シーンで今も記憶に残っている曲がある。ローリング・ストーンズの「タイム・イス・オン・マイ・サイド」だ。彼らの得意曲だったのか、とにかくその演奏がカッコよかった。で、私はそれがきっかけでストーンズという存在を知ったのだ。
思えばあの頃はこうしてグループサウンズのバンドが洋楽を演奏するのを観て(今聴くと、相当に怪しい演奏だったりもするが)、欧米のロックやポップスを知るということがけっこうあった。
そう思うと、グループサウンズが演奏する洋楽を聴くということは、そのまま洋楽ロックへの入り口に繋がっていたのだ。
今、ロックとポップスの歴史を知っている身として振り返ってみると、当時のグループサウンズの曲というのはその頃の欧米のロックやポップスとはまるで違う“洋楽風な歌謡曲”に過ぎなかったのだが、あの時代にラジオから流れるビートルズやローリング・ストーンズの曲を夢中になって聴いていた中学生にとっては、例え歌謡曲風であってもタイガースやブルーコメッツやスパイダースのオリジナル曲はやはり“洋楽”として聴こえていた。
なぜなら、ヴォーカルがいてギターがいてベースがいてドラムがいて、つまりはバンドだったからで、もう、それだけでカッコよかった。そしてそんなタイガースやスパイダースの延長上に、ビートルズやローリング・ストーンズが立っていたのだ。